6. 各種観察法の基礎
6. 6 変調コントラスト観察法 modulation contrast microscopy
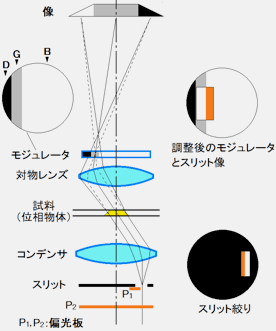
図6-12 変調コントラスト法の原理図
位相物体を可視化する方法として、1974年R. Hoffmannにより考案された変調コントラスト法(レリーフコントラスト法とも呼ばれます)があります。これは図6-12に示すように、コンデンサレンズの前側焦点面の光軸から外れた位置に矩形のスリットを置き、これと共役な対物レンズの後側焦点面にモジュレータを配置した構成になっています。このモジュレータは図のような透明(B)・グレー(G)・暗黒(D)の三段階の領域を持ったもので、スリット像はG領域に投影されるよう調整されます。スリットに付加しているP1とその下のP2は偏光板で、P2を回転させることによりスリットの幅と光量を変え、像のコントラストを調節することができます。試料にわずかな屈折率の勾配があると、スリットからの光は屈折し、モジュレータのBあるいはD領域へと振れるため、その部分に明暗のコントラストが付き、微分干渉法のような立体感のある像が得られます(図6-13)。変調コントラスト法は、位相差法の像に付きもののハローがなく、また微分干渉法のようにプラスチック容器が使えないといった制限もない、という利点があるため、徐々に普及してきています。
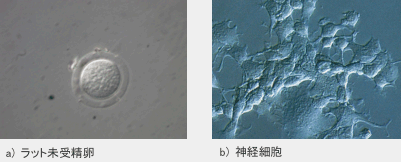
図6-13 変調コントラストによる像
