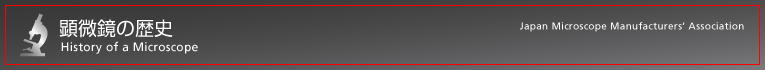6. 各種顕微鏡と周辺機器の始まり
6-7 位相差顕微鏡

図29
アッベの結像理論を研究していたゼルニケF. Zernike(オランダ:図29)は、1932年に無色透明な資料に光学的な方法で明暗のコントラストをつける位相差法を発表し、1941年ツァイス社と共同で位相差顕微鏡の試作品を完成しました。
これは、無染色の生物試料を生きたままで観察できる画期的なもので、細胞分裂の各段階における染色体の変化を連続的に見ることもできるようになりました。位相差顕微鏡は戦後になって急速に進展・実用化され生物学をはじめとする科学の発展に多大な貢献をしました。この画期的な発明により、ゼルニケは1953年にノーベル物理学賞を受賞しています。